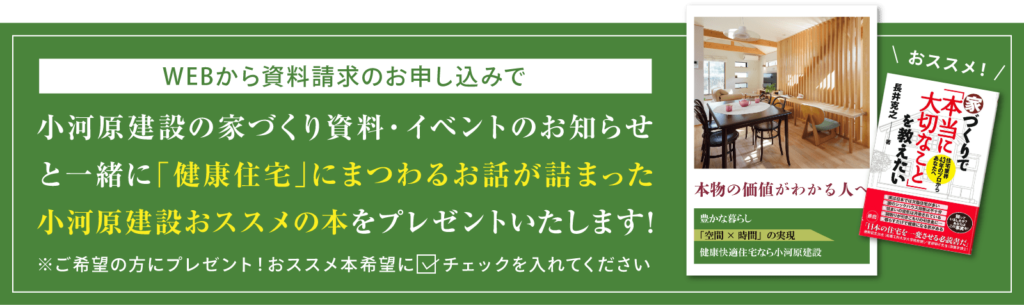近未来の家づくり-施工編-
7月に入り梅雨らしい日が続いていますが、皆様お元気でお過ごしでしょうか。
先月の本欄では「近未来の住まい」と題して、進化するIOT(家電や住設機器をインターネットにつなぐ)やICT(情報通信技術)を用いたスマートハウスと呼ばれる住宅での便利で快適な暮らしが、もうすぐそこまで来ていると話しましたが、今号ではその姉妹編として最新技術を用いた「近未来の家のつくり方」の一端ををご紹介します。
これまでの家づくりは木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造問わず現場にて鳶(とび)・土工が基礎をつくり、木造なら大工さん、鉄筋コンクリート造なら型枠大工と鉄筋工と生コン屋さん、鉄骨造なら鉄骨工と呼ばれる職人さんが、骨組つまり躯体の棟上げ(上棟)をおこない、仕上げ工事に入っていくという流れでした。昨今では職人さんの高齢化或は引退等での減少による人手不足を補う為、現場での作業を減らす為に、工場で壁や床を作りパネル化し、現場ではそれらを組み上げていく省力化・省人化工法が盛んに行われるようになってきていますが、画期的な工法が登場してきています。
国内外で建設現場への導入に向けて技術開発が進んでいる3Dプリンターによる建物(躯体)づくりです。
「プリンターで家をつくる?」ちょっとピンとこないかもしれませんが、欧米の先進企業では既に実用化されているのです。普通のプリンターはインキで紙に印刷しますが、建設用3Dプリンターはインキの代わりにコンクリートを吐出して、紙上ならぬ工場或いは現地で建物の躯体を作り上げていきます。
例えばアメリカのmighty billding社はHPでもアップしていますが、3Dプリンターによるモダンな感じの平屋の家を売りにしている。また、ドイツのPERI社はなんと2階建ての住宅の躯体を3Dプリンターを用いて二人でつくり上げています。3Dプリンターの特徴は工場で作った部材を現場で組上げるだけではなく、現場でも作業が出来る為、省人化・省力化が図れます。日本でも大手建設会社が公園のベンチとか橋桁などを作っていますが、技術開発が進み住宅などの建物に使われる日もそう遠くはないでしょう。
小河原建設のイベント情報はこちら
https://www.ogawara.co.jp/event/
最新情報はこちら
近未来の住まい
6月初めは梅雨の前に夏が来たような陽気が続いておりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
先日開催しました「未来の住まいコンテスト」では、様々なご提案を戴き、ありがとうございました。
今までにはない、何か新しいものを考えるときには、経験や知識、想像力が問われますが、私のようにこの道一筋40年以上ともなりますと、既成概念や先入観が邪魔をするもの。自由奔放な案を拝見し「こう云うのもありか!」と頭が少し柔らかくなった様な気がします。(笑)
そこで今回のブログでは「未来の住まい」を予測させる最新の状況についてお話ししたいと思います。
弊社の中野区大和町のモデルハウスもそうですが、地球温暖化防止の為、CO2削減を目的としたZEH(ゼッチ)と呼ばれる、性能の高い省エネ住宅が普及してきています。屋根に太陽光発電パネルを設置し、家の電気の使用状況を可視化したシステム(HEMS)を搭載したもので、スマートハウスとも呼ばれていますが、スマートハウスの発祥地は日本ではなく、実はアメリカなんです。あらゆるもので先進的な国だけあり、住宅に於いても日本より先行し、ZEH仕様の他に電気使用量の管理、ホームオートメーション、スマートロックやスマートスピーカ、センサーによるセキュリティなどの導入がハイピッチで進んでおり、2024年にはアメリカの家の約半数がスマートハウス化すると云われています。日本も後続ながら最近はコロナ禍やSDGsの影響もあり、スマートロックやスマートスピーカ等の導入も徐々に進み、2026年にはスマートハウスの普及率は40%ほどになると予測されています。
アメリカと違い、日本の場合は今後も少子高齢化の進展という課題を抱えています。家庭に於いても炊事、洗濯、片付け、掃除といった家事にかける時間を削減する為のホームオートメーションの設置が求められるでしょうし、増々増加する単身世帯には、スマートハウスによる見守り機能も必要となるでしょう。
おぼろげながら見え始めた近未来の住宅の姿ですが、共通して言えるのは、使用エネルギーの管理やホームオートメーション、セキュリティ、見守り機能などのスマート機能を持ち、そしてそれらを統合管理出来る「家全体のコントロールシステム」を備えた家ではないでしょうか。
近未来の家での暮らしはすぐそこまで来ています。
小河原建設のイベント情報はこちら
https://www.ogawara.co.jp/event/
最新情報はこちら
DX推進元年
「薫風爽やかに、木々の若葉が青空に映える季節です。」と時候のご挨拶で始まりたいところですが、
わが国は依然としてコロナ禍という暗い雲に覆われたままです。
世界を見れば、切り札となるワクチン接種が既に国民の50%程となり、地域によっては日常を取り戻している国も有るようですが、わが国の接種率は5月初旬時点で1〜2%と医療関係者にも、まだいき渡っていない状態とか、ようやく接種通知がきても日時の予約を取るのに電話もネットもパンクして繋がらないとか………😓。
今回の災禍は頻繁に経験する地震や台風等の自然災害ではなく、ウィルスによる未曾有の特殊災害とはいえ、もう少し速やかに、手際よく出来ないものでしょうか。非常事態時の対応で、その国の普段からの危機管理意識のレベルが分かるといいますが、オリンピックがほんとに出来るのか、少し不安になってきました。
さて、弊社の緊急事態宣言下でのお客様への対処方針については、紙面の関係で内容は割愛しますが、既にご案内している通りであり、変更はございません。
何かとご不便をお掛けしますが、引き続きご理解の程よろしくお願い申し上げます。
今回のコロナ禍も既に1年半近くになり、経済も社会も世の中が様変わりしてきていますが、建設・住宅・不動産業界でも同様、大手や先進的な企業を中心にVRでのモデルハウスや設計及び施工のリモートワークの実施、現場でのドローンやロボットの活用、営業やメンテナンスのAI活用などなど、予想された以上のスピードでIT化・デジタル化が進展し、業務の革新が行われています。我々中小企業も例外ではなく、同様に変革を迫られています。弊社もお客様により一層良い建物やサービスを提供出来る企業となる為に、今期52期を「DX元年」と位置づけ、ホームページ上でのVRモデルハウスのオープンやユーチューブ等のSNSでの情報発信、社内では工事、経理、総務などの各部門に於いて、IT化・デジタル化を進め、業務の改善に繋げていきたいと思っています。
52期も先月末で前半を終え、今月から後半に入っていますが、新卒2名と中途採用1名が新しい仲間として加わり、社内にも新しい風が吹き始めています。
また、来年の新卒採用では、初めてオンラインによる会社説明会等も行っております。内定者が決まりましたら、また本欄でもご報告させて頂きます。
小河原建設のイベント情報はこちら
https://www.ogawara.co.jp/event/
最新情報はこちら
換気の仕組みの再確認 その2
東京都は3回目の緊急事態宣言が発令されてしまいました。この時期昨年同様ですね。コロナ渦も長期化してくると少々疲れ気味ではないでしょうか。大型連休の前ですがわくわく感がありませんね。
気を取り直して前回の続きの住まいの換気について考えてみましょう。
24時間換気システムがない家の場合では一番簡便な方法は、トイレや浴室の換気扇を常時運転し居間やお部屋の外壁に直径10cm程度の給気口を設け、”空気の通り道”をつくることによって換気を確保することです。換気は空気の入口と出口を確保し、空気の通り道をつくることが大切で一方だけだと換気は出来ません。
また、気を付けて頂きたいのは、一般的なエアコンには換気機能はないということ。エアコンを運転すると空気が動くので換気されている様に感じますが(私もそうでした。(笑))、空気を循環させているだけです。最新のものには換気機能も付いているようですが、コロナ以前のものにはまず付いていないとみてください。
最近の住宅は高気密、高断熱化が進んでいますが、適切に機能させるには正しい利用とメンテナンスが欠かせず、それが効果的な感染対策にもなります。空気は目に見えませんから定期的に各種設備の点検・メンテナンスを行い、安心・快適な室内空気環境とする意識付けが必要です。
小河原建設のイベント情報はこちら
https://www.ogawara.co.jp/event/
最新情報はこちら
換気の仕組みの再確認
コロナ禍も1年以上となりコロナ疲れの感がありますが、感染予防には換気が大切だと云うことは、十分ご承知の通りです。
今回と次回2回に分けて換気の仕組みについて考えてみたいと思います。
この時期は花粉飛散とも重なり、また、中国大陸からは招かねざる客である黄砂やPM2.5などもやって来たりするので、うかつに窓も開けていられません。そこで本稿では窓を開けずに効率よく換気をするにはどうしたら良いか、考えてみましょう。
「換気」を辞書で引くと「建物などの内部の汚れた空気を排出して、外の新鮮な空気と入れ換えること」とあります。コップの水がかき混ぜないと腐ってくるように、閉じられた空間の空気も、何もしないと汚くなってくるものと思ってください。20年ほど前に新築の戸建てやマンションで入居者が体調を崩したり、アレルギー反応をおこすというシックハウス症候群が社会問題となりました。
当時使われていた建材に多くの化学物質が含まれ、片やアルミサッシなどの採用により住宅の気密性が高まっていたことによる室内空気の汚染が原因でした。それを受けて2003年7月にシックハウス規制法が施行され、室内空気の半分を新鮮な空気に入れ換える24時間換気システムの常時運転が、住宅に於いて義務化されてからは換気が確保されている筈です。筈と申し上げたのは電気代の節約のためにスイッチを切っていたり、給気口が閉じていたり或いはフィルターがほこりで目詰まりしていたりなどで、換気が出来ていないケースが多いから。換気扇の電気代は最近のものなら月数十円、古いものでも月数百円ですから、体調を崩すのと比べたら安いものです。フィルターのメンテナンス(洗浄や取替)も3ヶ月に一度位はやっておきましょう。24時間換気がトイレや浴室の換気扇と兼用になっているものも多いので、ご自宅の換気システムがどのようになっているか、今一度ご確認してください。
小河原建設のイベント情報はこちら
https://www.ogawara.co.jp/event/
最新情報はこちら
住まいの価値の見直し
1年以上に及ぶコロナ禍による社会や暮らしの様々な変化は、モノ的なことだけでは留まっていません。もっと、根本的な住まいの価値の見直しを迫っているとも言えます。テレワークにより、家族が家にいる時間が増え、家族仲が良くなったとか悪くなったとか、悲喜こもごものドラマが生まれ、結果、皆が家や家族の意味や価値を改めて問い直すようになってきています。
「住宅すごろく」という言葉がありました。振り出しは都会のアパート暮らし、次に、結婚して賃貸マンションを経て分譲マンション購入。そして、マンションを転売して郊外に庭付き一戸建て住宅を手にしたところで、上がり。と、いうのが昭和の時代に於ける住宅の一般的な消費者動向であり、30代40代の一次取得者層が中心でした。
平成の時代に入ると80代の親を持つ、50代後半から60代の二次取得者層の動きが多くなり、一戸建てを手にした後も建替えたり転居したりとすごろくは続き、上がり(最後)は介護施設に入所、というように消費者動向は変わってきてはいるが、住まいの価値としては駅から何分・土地は何坪・何LDKと資産としての価値ばかりに目がいっているように思います。このような流れの中でのコロナ禍であり、住まいの価値観がどのように見直されていくのか、大いに関心を持っているところです。
私が見直されて欲しいと思うのは、資産価値より、満足出来る家に長く住むことによって得られる情緒的価値です。何十年と長く住むことによって積み重ねられていく家族の思い出は、時間の経過と共にかけがえのないものになっていきます。
資産価値も勿論、高いに越したことはないが、それは家を売却する時しか生まれず、多くの人は相続の時まで家を売りません。
高齢化により、誰もが長生き出来る時代になり、家にいる時間も更に増えていくでしょう。長い老後を思い出の詰まった住まいで穏やかに過ごすことは、経済的合理性以上の価値があります。
小河原建設のイベント情報はこちら
https://www.ogawara.co.jp/event/
最新情報はこちら
コロナ禍で欲しいもの
寒さ厳しいこの頃ですが、膨らみ始めた梅の蕾が春の予感を感じさせてくれています。
皆様、お変わりございませんでしょうか。
コロナ禍となり1年が経ちますが、社会も経済も様変わりしてしまいました。
住宅・建設・不動産業界も同様で、営業・設計・施工・メンテナンスと企業活動の全ての分野に於いて、変化することを迫られています。
さて、本欄では前号でお伝えした「withコロナ、afterコロナを見越しての暮らしや間取り、住設機器などの提案」について具体的な内容をご紹介させて頂きます。
「どのような提案がなされているのでしょうか?」
会社というのはある意味、変化対応業です。世の中が変わればそれに合わせて、商品やサービスを変えていかなければいけません。
今回のコロナ禍によってもたらされた変化は大別すると、テレワークの普及(在宅ワーク対応)と三密の防止策(抗ウイルス対応)の二つです。前者により家は仕事をする場ともなり、在宅時間も増えました。後者では換気や非接触、遠隔操作といったことが求められています。
暮らしや間取りの提案は前者に対するもので、家の中に仕事場(ワークスペース)を確保し、気分転換や家族との触れ合いの為に中庭やインナーテラス、アウトドアリビングや広いバルコニーといった中間領域(中でも外でもない場所)を設けたプランが主に提案されています。
仕事をする場(ワークスペース)はLDKや寝室、廊下などの一画や収納スペースをリフォームしたりと、いろいろ工夫して何とかなるとしても、気分転換の為に中庭などの中間領域を設けるのは、郊外の広い家ならいざしらず、都心の決して広いとは言えない家の場合は、広さ的に難しいのが現実です。
この場合は屋根の一部を屋上テラスとして出入り出来るようにするのが良いですね。
また、玄関脇に手洗いを設けたり、玄関から直接洗面所に行けるように動線を変えた間取り等も登場していますが、これなどはコロナが収束したらどうするのでしょうか !? 気になるところです。
次は住設機器などの提案についてですが、キーワードは「換気」と「非接触」です。順に述べていきますと、
・換気が出来るエアコン
今までのエアコンは換気が出来なかったとは! 気にしてなかったですね。
・ドアを閉めたまま採風出来る玄関扉
コロナ対策で換気が求められている今、玄関扉を開けて風を通らせたいところ
ですが、防犯の心配がありました。両方を成り立たせるのが採風可の玄関扉。
・タッチレス水栓
駅、高速道路、病院などのトイレの水栓は今やほぼタッチレス。自宅の水栓もタッチレスで家族からの感染を防ぎます!
・シャワートイレ
「日本人のコロナ感染者数が先進諸国と比べて低いのはシャワートイレの普及率が高いからかも?」と誰か言われていましたが、便や尿にウィルスが含まれる可能性が高いとのことで、ペーパーでお尻を拭く際、微妙に手に付きドアノブ等を通じて家族に感染する可能性があるのだそうです。それを防いでくれるのがシャワートイレ。
・IOTアシスト
スイッチを家から一掃します。声で照明やテレビをオンにし、お風呂は外からお湯張り、沸かし。
家族間の接触頻度を極度に減らします。
・宅配ボックス
多くの人と接する宅配のお兄さんとの接触頻度は極力減らしたいところ。
集合住宅向けのイメージが強かったが戸建てにも浸透してきています。
ここ1、2年で一万円を切る安価なものも提案されています。
・システム収納
在宅勤務やオンライン授業を家で行うようになり書類、電子機器類の収納が欲しくなります。
以上、主なものをいくつか上げてみました。中には一過性のものもあると思いますが、何か興味を持たれたものがありましたらお気軽にご相談ください。
皆様のお役に立てれば何よりです。
小河原建設のイベント情報はこちら
https://www.ogawara.co.jp/event/
最新情報はこちら
新年のご挨拶
あらためまして、新年おめでとうございます。
東京は三が日とも爽やかな冬晴れの中、私は家でおとなしくお正月を過ごしておりました。
皆様はいかがお過ごしされたでしょうか。
正月休みも足早に過ぎ去り、弊社は4日から平常通りに業務を始めております。
さて、今年の年明けを振り返るに、経済を占う株式市場の大発会では、昨年と同様、安値での始まりでした。
縁起を占う豊洲の初競りでは、去年は一本のマグロに1億9320万円(一昨年は3億3360万円)の値が付いたのが、今年は2084万円だとか。
コロナ禍の中、どこも正月気分どころではなかったようです。
この記事を書いている最中にも緊急事態宣言が発令され、正月気分も完全に吹き飛んでしまった感じですね。
先の読めない2021年の幕開けに際し、今年の注目すべき行事を上げると
1 月 アメリカ大統領就任式
3 月 G7主要国首脳会議(英国)
7 月 東京オリンピック開催
8 月 東京パラリンピック開催
9 月 デジタル庁発足
10 月 衆議院議員総選挙(予定)
などが上げられますが、やはり最大の関心事は「コロナ禍がいつ収束するのか」、「東京5輪は開催されるのか」、ではないでしょうか。
何が起こるか分からない、否何が起こっても不思議ではない昨今の世の中です。
最善だけではなく最悪の事態も想定し、備えをしておくことが肝要です。
冒頭にも記しましたが、コロナ禍が2年目を迎えた早々、2回目の緊急事態宣言が発令されました。
宣言が解除されない限り、景気は厳しくなる一方ですが、住宅・建設業界でも手をこまねいているだけではなく、大手を中心にwithコロナ、afterコロナを見越しての暮らしや間取り、住設機器などの提案が盛んに見られるようになってきています。(これについては来月号の本欄でお伝えしたいと思います。)
弊社もこのような状況の中、コロナ禍を奇貨とすべく、この1年を乗り切っていくつもりです。
大変な状況ではありますが、今年も皆様のお役に立てるように、またお楽しみ頂けるようにスマイルニュースに取り組んで参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 感謝
小河原建設のイベント情報はこちら
https://www.ogawara.co.jp/event/
最新情報はこちら
丑(うし)年ってどんな年?
子年(ねどし)が変じて、”コロナ年”となった今年も残りわずかとなりました。
皆様お元気でお過ごしのことと拝察いたします。
昨年末の本欄では、今年の干支の庚子(かのえ・ね)年について「変化への動きがあり、新しいものを作り出していく年」と記しましたが、まさしくコロナ禍を契機とした大変化が、新常態をつくり出したこの一年であったと思います。
来年は辛丑(かのと・うし)、辛丑とはどのような年なのか調べて参りましたので、早速、ご紹介させていただきます。
まずはおさらいをしましょう。
「干支」とは十二支(じゅうにし)を指しますが、本来は「十干(じっかん)」つまり甲(こう)乙(おつ)丙(へい)丁(てい)戊(ぼ)巳(き)庚(こう)辛(しん)壬(じん)癸(き) に「十二支」(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)を順番に割り振っていった「十干十二支」(じっかんじゅうにし)のことを言います。
甲子(きのえね)に始まり、癸亥(みずのとい)で終わる60通りの組み合わせがあることから、六十干支(ろくじっかんし)ともいい、古くから暦や時刻、方位等の表記に用いられてきたものなんですね。
ここからが本題です。
十干の8番目に当たる「辛」(かのと)は、植物で云うと「草木が枯れ、新しくなろうとしている状態」を表し、下にあるエネルギーが上に上がってくるような新たな状態、また字としては新しいと同時に”からい”という意味などもあり、陰陽では陰に分類されています。
「丑」(うし)は十二支の2番目で、植物に例えると種から芽が出ようとする状態を表し、曲がっていたものが伸びるとか、始める、結ぶ、つかむと言った意味があるようです。
丑の語源は、赤ちゃんは出生時に手をにぎりしめている事からとされ、誕生・創造などもイメージ出来ますね。
また、丑年は五行では水気、陰陽では陰に分類されています。
ちなみに、「五行」とは、古代中国の自然哲学の思想で、万物は木・火・土・金・水の5種類の元素からなるという説であり、「陰陽」とは、これも中国の思想で森羅万象、宇宙の全ての事物を様々な観点から「陰」と「陽」に分類する考え方です。
それでは来年の「辛丑」年の運気や兆候についてまとめていきましょう。
「辛」は新しくなること、エネルギーの現出であり、「丑」は芽吹き、伸長を表し、共に似たような意味を持っています。
よって来年は簡潔に「誕生し新たな試みをする年」と言えそうです。
過去の丑年を振り返ると、人類初の宇宙飛行や、日本では自民党から民主党への政権交代、ハイブリッド車のデビュー、コンビニ1号店出店など革新的な出来事もありました。
2020年は新型コロナウイルス・パンデミックによって世界中が多くの困難に見舞われました。
2021年はコロナを克服し、その中から数々のイノベーションが生まれ、希望に満ちた年になるとよいですね。
東京オリンピックの来年開催を信じて疑わない私としては、開催を契機に東京が更に住みやすい魅力的な街になることを期待しています。
来年が皆様にとってすばらしい年でありますように。
感謝

▽▲▽▲▽▲▽▲小河原建設の住まいづくり資料請求はこちら▽▲▽▲▽▲▽▲
——————-都心で暮らす本物の木の家モデルハウス——————
<完全予約制にて公開中!!>
https://www.ogawara.co.jp/event/id1479/
********小河原建設YouTube*********
「現場キレイ」「モデルハウスルームツアー」などなど
見どころ満載!!
https://www.youtube.com/channel/UCgrhem9I3neg60Qn3seAO4w
その他最新情報はこちら🏠↓↓↓↓
進むデジタル化/コンテスト開催します!
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
11月も後半となり、コロナ禍も日常化した感がありますが、個人的に気になっていることがあります。
昨今の身の回りに溢れるカタカナ英語の多さです。
どうにかならないものでしょうか。
日本人のカタカナ英語好きは、コロナ禍やデジタル化によって増長する一方のようです。
最近は単語だけではなく「go to ○△」と文章にもなってきた。(笑)
知識人と言われる人ほどカタカナ英語を使うのが好きな人種のようですが、日頃、日本語を大切に使いたい私としては、減るどころか増える一方のカタカナ英語表記の多さに、内心戸惑いを感じています。
日本語には、例えば「後生を願う」とか「冥利に尽きる」など、美しい言葉がたくさんあります。
一見、古臭い言葉でいまどき通用しないように思いがちですが、日本の伝統の中で語り継がれてきた言葉には大きな力が秘められています。
カタカナ英語は調べないと分からないし、何か分かったような気になってしまうところが怖い。
私に賛同していただける御仁がいらっしゃればこころ強い限りです。
共に「日本語を守る会」を立ち上げましょう。(笑)
さて、コロナ禍の日常化やテレワーク、オンラインなどのデジタル技術の普及により、仕事のやり方や暮らし方が変わりつつあります。
またもカタカナ英語で恐縮ですが、最近、注目したい言葉に「DX」なるものがあり、かまびすしい程メディアの紙面を賑わせています。
デジタルトランスフォーメーションといい、ITやデジタル技術を導入して仕事の効率を高めるだけではなく、もっと深く会社のシステムや方針までも変革し、競争優位に立とうというものです。
日本の会社は欧米や新興国の海外勢に比べると、ここら辺がかなり遅れているらしいので、国もデジタル庁などを新設して応援体制に入ったようです。
会社も住まいもどのようなものに変わっていくのでしょうか、気になりますねー。
ですが、未来のことなので誰にも分かりませんよね。
そこで「分からない時はお客様に聞け」とばかりに「未来の住まいコンテスト」なるものを企画しました。
2月に「お客様感謝ディ」を開催以来、イベント等は自粛しておりましたが、コロナ禍でもお客様にご参加して頂けるようなことは出来ないかと考えたものです。
「コロナが収束したらこんな家に住みたい」「こんな住み方もあってもいいよね」等など、どのようなことでも結構ですので、近未来の暮らしや住宅に対する思いやイメージを聞かせて戴ければと思います。
小河原建設のイベント情報はこちら
https://www.ogawara.co.jp/event/